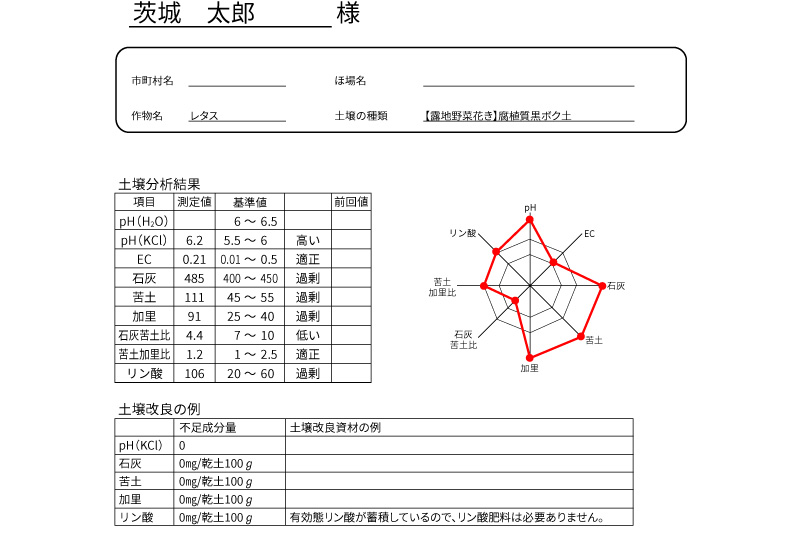私が北陸農業試験場(新潟県上越市)に勤務していた1980年代中頃に、北陸地域では10ha規模の稲作経営が台頭してきていました。特別栽培米制度ができ、特別な栽培方法で生産した米を、特定の消費者に直接販売することが合法になりました。それまでは米の生産者は、農協や卸売業者などの許可を得た者だけに、生産物を販売することになっていました。それ以外の業者などに販売する米は「ヤミ米」という違法なものであるとされていました。
米にしても野菜にしても、農家が個別で販売する場は少なく、農協や市場に出荷、つまり販売委託をしており、農産物の価格を生産者自身が決めることができないのが普通でした。この特別栽培米制度開始以来、先進的な稲作経営者は、自ら販売すること、消費者と直接取引をすることにより、「生産者」から「経営者」へと大きく性格を変えていきました。自分の生産した農産物の価値を消費者から伝えられ、さらに「こんな米を食べたい」という要望を聞くことにより、消費者に食べ物を届けることの意義に目覚めたと言えます。
現在のトップ経営者が生まれた契機
この、販売に目覚めた経営者が農業法人を設立して、現在に至る先進農業経営を主導してきたと言えます。年代で言うと、1980年代後半から1990年代初頭の事です。米だけでなく野菜作でも同様で、例えば千葉県香取市の「農事組合法人和郷園」の代表理事である木内博一氏の著書「『結農』論」を見ると、それまで千葉県内の市場に出荷していたホウレンソウを、小売店のバイヤーのリクエストにより、無農薬・無化学栽培で生産し、東京までトラックで運んで納品することにより、地元市場への出荷の9倍の価格で販売することができたとされています。この経験により、農家ではなく「農業経営者」を目指すようになったとしています(※木内博一 「『結農』論」pp44~49 亜紀書房 2016年)。年代は1990年代初頭です。
こうした、生産者から農業経営者への転身の契機については、他の農業法人の代表者も、著書の中で述べています。長野県御代田町で「有限会社トップリバー」を創設した島﨑秀樹氏の著書『儲かる農業』によれば、トップリバーの特徴の第一に書かれているのは、「市場出荷ではなく契約栽培がメイン」であるとされています(※嶋崎秀樹 『儲かる農業』pp45~49 竹書房 2009年)。つまり、市場取引の結果として、価格が後から決まるのではなく、取引に先駆けて事前に、価格も含めた取引条件を決定することを、自らの経営の特徴としているのです。さらに、群馬県昭和村で野菜くらぶグループを牽引している澤浦彰治氏は、『農業で成功する人うまくいかない人』の中で、自分で生産物の価格を決められない状況から脱却するために、コンニャク芋を板コンニャクやシラタキに加工して販売したとしています(※澤浦彰治 『農業で成功する人うまくいかない人』pp177~178 ダイヤモンド社 2015年)。
このように、現在、日本農業のトップグループとみなされる農業法人のいくつかを見ても、「自分で農産物の価格を決めたい」と考え、市場や農協以外の販売先や販売方法を見出し、あるいは農産物加工に取り組むことにより、他にない差別化をした商品を作り出す取り組みをしたと言えます。彼らは、自ら生産した農産物に自ら価格を付けることにより、「農業生産者」から「農業経営者」に性格を変えたと言えます。
販売を起点に農業経営を考えることの重要性
農業経営を行う以上、年度当初に、黒字を出すような経営計画や財務計画を作成する必要があります。そのためには、いくらで販売できるのかという、販売単価の設定が重要です。生産物はいくらの単価で販売でき、どれくらいの単収を上げれば、バランスシートは均衡するのか。販売単価がいくらなら、どこまでのコストをかけても利益が出るのか。そうしたことを考えて生産計画を作成する必要があり、つまり、販売を起点にして経営を考えることが必須となります。コストの中には、経営者自身の報酬や家族員の労賃も、当然のことながらきちんと算入する必要があります。自作地地代や自己資本利子についても同様です。よく分からないが、経営外に支払う経費を除いた金額で、何とか食べていければ良いという農業は、若い人には受け入れられないでしょう。
もちろん、農業生産は天候によって左右されるので、生産物の収量や品質は、必ずしも計画どおりには実現できません。そのためもあり、販売契約を結んだとしても、播種前の販売単価や数量は大まかなものであることが多く、収穫・出荷までに、生育状況や市況に応じて、契約の調整が必要になります。しかし、工業製品のように計画どおりの生産は難しくても、計画的な生産を行う事は重要です。経営収支で赤字が出た場合も、その原因を分析し、翌年の生産に生かすことができます。
これに対して、従来の生産を起点にした考え方では、市場で評価される大きさや規格の農産物を多収することを目標に生産を行いますが、結果的に儲けを出せるかどうかは、その年の単収と単価次第なので、「今年は儲かった」「今年はダメだった」で終わり、翌年の生産に役立てる分析的な考察を得ることはできません。
優れた農業経営者は誰が食べるのかを想定して農業生産を行う
10年くらい前になりますが、茨城県内のトマトを生産する農業法人を訪問した際、社長の説明に感動しました。以前は、東京の市場でトップの単価を取る、糖度の高いトマトを生産していました。しかし自分の農場の近隣の人は、誰も自分のトマトを知りません。それでは面白くないという事で、県内のスーパーで販売される、普通のサラリーマンが毎日購入できるような価格のトマトの生産に切り替えました。
販売単価を下げるには、コストや収量の目標を変更する必要があり、当然、目標とする糖度も変えました。誰がいくらで購入し、どのような状況で食べるトマトなのか、それを見極めてから生産計画を立てるという事で、まさに経営学の教科書の内容そのものだと思いました。
農産物の販売方法の多様化と課題
農産物の販売ルートは多様化しています。小規模農家や高齢農家にとっては、2000年前後から開設が進んだ農産物直売所が、有利な販売先となっています。自分で価格を決められますが、売れ残りは引き取らなければなりません。一方、高い生産技術を持ち、自身では生産に特化した農業経営を行いたいと考える生産者は、販売を農協に委託することが多いと思われますが、基本的には販売単価を事前に知ることはできません(契約栽培に取り組んでいる意欲的なJAも一部にはあります)。また、大規模な経営では、全農茨城県本部のVF事業において栽培契約を結び、生産物を販売することも可能です。VF事業では、契約農家や農業法人の生産物を買い取り、量販店・生協・業務用などへの販売を行っています。さらに、前述した、和郷園グループ・トップリバーグループ・野菜くらぶグループなど、農家や農業法人をメンバーとするネットワーク型の販売組織を通じて販売を行っている生産者もいます。
現在はこのように、自らの経営の特質に応じた販売方法の選択が可能になりつつあると言えましょう。こうした状況下で、今後の地域農業の担い手を考えていく際に最も重要なのは、売上金額で1,000~3,000万円程度の、法人化をしていない家族経営の最上層ではないかと思います。自らが単独で販売や営業活動を行うのは難しいが、需要側のニーズを的確に捉えて、販売起点の農業経営を行っていかなければ継続発展は難しい、大規模な家族経営は販売をどうすべきか、ということです。そのための、農業経営間の組織化について、次の回で考えてみたいと思います。